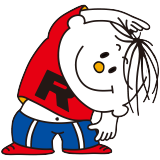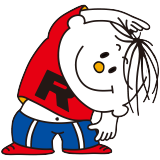|
1.13種類の運動をおよそ3分間で行い、できるだけシンプルでわかりやすい運動で構成されています。
2.各運動の配列に、よく考えられた以下のような特徴があります。
・全身を均等に動かすように配慮しています。
・運動強度は全体としてやさしめに作られています。
・運動強度がやさしめに作られた中でもさらに運動に強弱があり、はじめは緩やかに、徐々に強さを増し、中間にて強度のピー
クを作り、終わりに近づくにつれ強度を緩やかにして、体に負担を残しにくい構成になっています。
3.運動強度の目安となる心肺機能の負荷は、脈拍数で見ると一般的に90~100拍/分となるように作られています。
体操全体の速さを平均すると「はやあし足踏み」のテンポ(110拍/分程度)で行うようにできています。
4.13種類の一つ一つの運動がねらいを持っており、体の部位ごとに運動の方法と目的とする効果を定めています。(これはラ
ジオ体操第1、ラジオ体操第2、みんなの体操すべてにすべてに当てはまり、この「ねらい」を意識して各運動を行うことは、
運動効果を高めることにつながります。)
5.有酸素運動です。(よって呼吸を止めずに行うことが大切です。呼吸を止めずに行うことで、各筋肉はよく伸展し、運動効果
を高めることができます。)
|